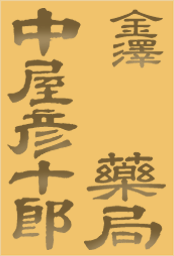エラブウナギ<健康食品>
エラブウナギとは
健康補助食品
鹿児島県沖永良部島近海で捕れるところからその名がある。
沖縄県久高島ではイラブ又はエラブウナギと称している。
「特徴」
身体は太く短い(体長70〜120センチ)
体色、形状は
Reinwardt:青灰色で縞の輪紋がうすい、頭が小さく吻はまるい。
Schneider:鮮やかな黒とブルーの縞の輪紋、頭は小さくて吻は丸い。
尾部はウナギのように扁平。肺呼吸をし、子魚(熱帯魚のウツボなど)を常食。
毒牙と毒腺を持つ。
水温24℃〜25℃の暖かい所を好み、30日〜50日飲まず食わずでも生きる。
性格は大変おとなしい。
「生態」
主に沖縄から東南アジア、オーストラリアの珊瑚礁海域に生息している。
昼間は海岸の岩陰に潜んでおり、ときどき餌をとりに50~30メートルの海底を泳ぎ回る。
砂の中にもぐるため、動きやすいように尾がウナギのように丸く膨らんでいる。
旧暦の6月頃~12月は交尾と産卵のため久高島の海岸の洞穴に、夜間に海から上がってくる。
卵をもったイラブがもっともよくとれる時期は10月中旬。
岩の割れ目に4〜5個の卵を生む。
「漁業権」
エラブウナギの漁は、旧暦の六月頃から12月に久高島の海岸の洞穴(ガマ)に、交尾と産卵のため海から
上がってきたところで素手で捕獲する。
久高島では、旧暦6月24日から12月30日までの産卵期しか捕獲が許されていない。
捕獲権は特定の人(ノロ)に限定されている。
「エラブトキシン」
は神経毒で、水中で獲物を弱らせ暴れて逃げたり反撃させないために使う。その毒性はマウスの半数致死量
LD50で比較するとハブの約10倍の強さである。
しかし、エラブトキシンは蛋白質であるため、熱をかけると変性し、失活する。
「食の歴史とエラブ」
沖縄では500年も前から「イラブ料理」として、燻製や煮たり焼いたりスープにした料理を滋養強壮や民間薬的に
珍重してきた。エラブウナギの入手が困難であるため、もっぱら王族や上流階級の人々のみが口にしていた。
保存性に優れた燻製品は、大陸との交易のさいに皇帝への貢物とされた。近年食べやすく加工したものが
販売されている。
エラブウナギ(エラブウミヘビ)油
エラブウナギは、EPA(エイコサペンタエン酸)DHA(ドコサペンタエンサン)を含む小魚を食べてEPAやDHAを
体内の脂肪組織に蓄えています。
脂肪組織から抽出した油のなかには、EPAやDHA,リノール酸やリノレイン酸などの脂肪酸や、ビタミンA,
ビタミンE、ミネラル、リン脂質が含まれています。
EPA・DHA・リノール酸などの高度不飽和脂肪酸は、私たちの体内で作られにくい必須脂肪酸で、積極的に
魚類から摂取したほうが効率的といわれています。
野菜やシソ油を摂取してEPA・DHAを作るには、野菜やシソ油のα-リノレイン酸が腸の上皮細胞に吸収され
、リンパ管を通って静脈に入り、肝臓においてEPAに変化し、その後、 必要な分だけEPAがDHAに変化する
ことがわかっていますが、その量は魚を食べるときよりはるかに少ないといわれています。
魚油に多く含まれるEPA,DHAは、シソ油や野菜油など植物系の油ばかりのα-リノレイン酸系の油に分類
されています。 炭素数が20個~22個の短い脂肪酸です。
海中生物の食物連鎖は植物プランクトンから始まりますが、この植物プランクトンにα-リノレイン酸が含まれて
いて、これを動物プランクトンが食べてEPA,DHAが作り出され、さらに動物プランクトンを小魚が食べ、小魚を
エラブウナギが食べて蓄えるのです。
|
エラブウナギ 日本 蒸し焼き 70〜100g
|
|
エラブウナギ 180粒
|
©2001 - 中屋彦十郎薬舗株式会社 All rights Reserved.
プライバシー保護方針 特定商取引法に基づく表記 
本社・薬局/通信販売
〒920−0981 石川県金沢市片町1丁目1-29 TEL 076-231-1301/FAX 076-231-1306
工場
〒921−8117 石川県金沢市緑が丘21-9 TEL 076-245-3366
|