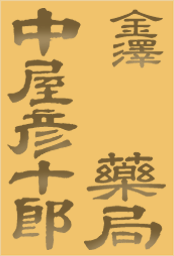●人参(ニンジン)

第三類医薬品、漢方・生薬の人参は朝鮮人参、高麗人参と言われ、神農本草経の上品にも収載され、古くからもっとも珍重された補薬です。その根が人の形に似ているから名付けられたといわれています。
(起源)
人参はウコギ科のオタネニンジンの細根を除いた根 (生干人参) 。オタネニンジンの細根を除き、根の外皮を除いたものを白参という。またはこれを軽く湯通しして
(御種人参、雲州仕立て) 乾燥したもの。人参はその調整法により「白参」と「紅参」に大別できる。もっとも雲州仕立てのような中間型もある。白参は直参、半曲参、曲参にわけられる。日本産、開城人参などは直参、豊基人参は半曲参、錦山人参は曲参で、そのほか生産地により数種の形の人参がある。紅参は細根をつけたまま蒸しあげ乾燥したもの
(日本産紅参) と、細根を除去し圧力をかけて乾燥したもの (北鮮、韓国産紅参) とがある。細根のみは鬚人参。
(産地)
日本(長野、福島、島根;栽培) 、韓国、北朝鮮、中国、ロシア (栽培、野生品はきわめてすくない。)
(成分)
精油0.05% (β-エレメン、パナキシノール、パナキシドール、ヘプタデカー1-エンー46ジインー39ジオール、サポニン配糖体約4% (ギンセノシドなど)
、糖類約5%を含む。
(臨床応用)
虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症などに応用する。
(処方例)
白虎加人参湯、生姜瀉心湯、小柴胡湯、人参養栄湯、理中丸など。
(用法・用量)
煎剤、丸剤、散剤。1日0.5〜3.0グラム。韓国では健康増進に12〜20g/日、病中病後の体力回復に20〜50g/日を使用する。
(同類生薬)
- 広東人参:アメリカニンジンの根を乾燥したもので、カナダ、北アメリカに産する。別名を「西洋参」「花旗参」などともいう、成分としてサポニン配糖体
5%、を含み、用途は人参と同様に用いる。
- 三七人参:サンシチニンジンの根を乾燥したもので、「田七人参」「田三七」などともいう。中国雲南省、広西壮族自治区およびベトナム北部に産する。成分としてサポニン配糖体3〜8%を含み、その主成分はギンセノシドである。

|
人参 中国 生干(きぼし) 刻み 500g
|
|
人参 中国 生干(きぼし) 丸切 500g
|
|
人参 中国 御種(湯通し) 刻み 500g
|
|
人参 中国 御種(湯通し) 丸切り 500g
|
|
人参 日本 御種(湯通し)刻み 500g
|
|
人参(保存液漬け) 日本 285g 特大一本
|
|
人参(白参) 中国 原形 100g 4〜6本
※根の細根と外皮を除き乾燥したもの
|
|
人参 生干 中国 粉末 500g
|
|
鬚人参(毛人参) 日本 生 500g
|
|
鬚人参(毛人参) 日本 刻み 500g
|
|
鬚人参(毛人参) 中国 生 500g
|
|
高麗人参 韓国 6年 直参(15根入り) 300g
|
|
高麗人参 韓国 4年 曲参(30根入り) 300g
|
|
人参エキス末 100g
|
©2001 - 中屋彦十郎薬舗株式会社 All rights Reserved.
プライバシー保護方針 特定商取引法に基づく表記 
本社・薬局/通信販売
〒920−0981 石川県金沢市片町1丁目1-29 TEL 076-231-1301/FAX 076-231-1306
工場
〒921−8117 石川県金沢市緑が丘21-9 TEL 076-245-3366
|