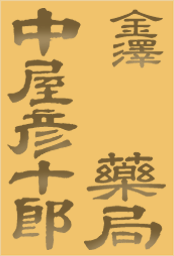|
漢方生薬の中屋彦十郎薬局 / 会社案内
漢方生薬の中屋彦十郎薬局TOP >生薬の通信販売一覧>黄連(オウレン)
●黄連(オウレン)

第二類医薬品 黄連は神農本草経の上品に収載されている。
起源
- 日本産:キンポウゲ科のオウレン (セリバオウレンおよびキクバオウレンなど)の根を除いた根茎である。
日本国内には幅広く野生する、多年草である。
草の丈は10~20cm、地下茎が横に伸び多数の髭根をだす。
葉は長い柄で根茎から叢清生し、さらに小花をつける。
早春に1cmほどの白い花を花茎の先端に数個開く。
薬用にする根茎の断面は鮮やかな黄色である。なめると苦い。
黄色い根が連なるのでこの名がある。
栽培されているのは小葉の形がセリの葉に似たセリバオウレンと、キクの形に似たキクバオウレンの二種類である。
自生のミツバオウレンやコセリバオウレンは根茎が小さいので薬用には適しない。丹波、越前などが主産地である。
畑にまいたものは4~5年後に根茎を掘り下げ、水洗いしないまま日干しにする。
生乾きのころに焚き火の中に根茎をいれてひげ根を焼き、手にわらじをはめてむしろに広げた根茎をこすり、焼け焦げのひげ根を除いてから天日で干す。これで黄連のできあがりである。
- 中国産:味連 (四川、湖北、陝西南部など) 、雅連、峨眉連、峨眉野連 (四川省峨眉、洪雅で栽培)の根茎、および鳳尾連、峨眉野連 (四川省峨眉、洪雅の野生品)の根茎もしくは根茎つき全草、これらを「川連」と称する。
- そのほか「雲連」あるいは「ビルマ黄連」など。
成分
アルカロイドを主成分とし、ベルベリン含量は局方3.5%以上である。
このほかコプチシン、パルマチン、オウレニンなどを含有する。
ベルベリンは苦味が強い。ベルベリンは黄柏の主成分でもある。
漢方では黄連の性質は大苦・大寒で瀉火・燥湿・解毒の薬能である。
「心下を瀉し、胃腸の湿熱を清し、湿と熱の鬱結を治療する要薬」といわれている。
黄連・黄ごん・黄柏はいずれも苦寒薬で効能もよくにているが、古来より「黄ごんは上焦を治し、黄連は中焦を治し、黄柏は下焦を治す」と説明されている。
中焦というのはおもに胃腸のことで、黄連はとくに嘔吐や下痢、腹痛などの胃腸症状に好んで用いられる。
効能・効果
胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢
使用上の注意
1.次の人は服用前に医師,薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)発熱を伴う下痢のある人,血便のある人又は粘液便の続く人
(3)高齢者
2.1ヵ月位(止瀉で服用の場合は5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し,この製品を持って医師,薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
用法・用量
<刻み・丸切> 大人(15歳以上)は1日量3gを、水約300mLで約半量になるまで煮つめ,かすをこして取り去り,食前または食間3回に分服する。(食間とは・・・食後2~3時間を指します。)
<粉末>大人(15歳以上)は1回量0.5g、1日3回、食前または食間に服用する。(食間とは・・・食後2~3時間を指します。)
応用
苦味は後までのこるが、胃の活動を盛んにし、腸内を静菌する働きがある。
根茎を濃く煎じた汁を口に含んで口内炎にも用いる。
処方例
黄連解毒湯、三黄瀉心湯、柴胡清肝湯、荊芥連翹湯、清上防風湯など。
用法・用量
煎剤、散剤、丸剤。1日0.5~3.0g。0.1~1.5g (末) 。
保管及び取り扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になります。)(4)開封後は,輪ゴムなどで封をして保管してください。
黄連はキンポウゲ科に属する背の低い常緑の多年草で、山地の 樹下、陰地に自生しています。栽培も行われています。
雌雄異株で早春に10センチほどの花茎をだし、白色の花を2~3個つけます。
黄連にはキクバオウレン、セリバオウレン、コセリバオウレンがあります。
金沢市の近郊に医王山という海抜1000メートルの山がありますが、藩政時代より薬草の宝庫といわれています。
この山にも黄連が自生していますし、所によっては栽培もされています。
薬草のなかではもっとも高額になるものです。
7~8年たったもので採取してから水洗いし乾燥して、ヒゲ根を焼いて取り揃えていきます。
これを10キロ位まとめれば売買の対象になるでしょう。
金沢近郊でとれるものは加賀黄連、福井県大野地方でとれるものは越前黄連とよばれています。
その他、全国各地、鳥取、島根、新潟、広島、兵庫、福島などでとれます。輸入品もあります。
輸入品は中国、ミャンマー、ベトナム産です。噛んで苦く、唾液が黄色くなるものがよいとされています。
良薬口に苦しの典型的なものでしょう。
苦味健胃剤、整腸、鎮静剤として幅広く使われています。
三黄瀉心湯、黄連解毒湯、清上防風湯、半夏瀉心湯などに配合されています。

|
黄連 中国 刻み 500g
|
|
黄連 中国 丸切 500g
|
|
黄連 中国 粉末 500g
|
|
黄連 日本 原形 500g
|
|
黄連 日本 粉末 500g
|
©2001 - 中屋彦十郎薬舗株式会社 All rights Reserved.
プライバシー保護方針 特定商取引法に基づく表記 
本社・薬局/通信販売
〒920-0981 石川県金沢市片町1丁目1-29 TEL 076-231-1301/FAX 076-231-1306
工場
〒921-8117 石川県金沢市緑が丘21-9 TEL 076-245-3366
|