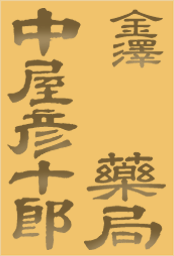●竜胆 (リュウタン、りゅうたん)

第二類医薬品、神農本草経の上品に収載されている。
(起源)
日本特産の植物でリンドウ科のトウリンドウ、またはそのほか同属植物の根および根茎。本来は関東以西の山野に自生していた。
茎は直立か斜め上にのび、葉は対生して柄がなく、茎を抱きこむようにつく。全縁で縦に走る三本の脈が目立つ。
源氏の紋所は、リンドウの花と葉を巧みに図案化したものだという。
薬になるのは根。秋に根を掘り取り、水洗いして日干しにしたのが生薬の竜胆である。
薬局方にも収載されている生薬である。ゲンチアナ根に代用できる。
中国産の「関竜胆」 (東北諸省産)のなかには、G.trifloraPALLASの地下部を混じている。また「雲南竜胆」「貴州竜胆」 (雲南、貴州、四川省産)
はG.regescensFr.の地下茎部を起源とする。
かって日本産の「樺太竜胆」または「蝦夷竜胆」と称する生薬が市販されたことがあるが、このものの起源はエゾリンドウの地下部であったが、今日では市場性はない。
(産地)
中国 (東北諸省、内蒙古、浙江、安徽) 、韓国、日本(長野、北海道) 。
(成分)
モノテルペン配糖体 (苦味配糖体)のゲンチオピクロシド、スエルチアマリン、スエルチオシド、トリフロシドなどのほか、キサントン誘導体のゲンチシン、糖類のゲンチアノース、ショ糖などを含有する。
(応用)
胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき。ゲンチアナと同様に用いる。民間療法では消化不良や食欲不振に用いられてきた。
苦味が舌先を刺激して、大脳反射により胃液の分泌をうながすという。
(処方例)
竜胆瀉肝湯、疎経活血湯など。
(用法・用量)
煎剤、散剤、丸剤。1日1〜3グラム。
竜胆三グラムを500mlの水で半量になるまで煎じ、これを一日量として三回に分服する。

|
竜胆 中国 刻み 500g
|
|
竜胆 中国 粉末 500g
|
<使用上の注意>
体質や体調により合わない場合は摂取を中止してください。
<取扱上の注意>
- 開封後は、性質上吸湿することがありますので、湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい場所に保管し、なるべく早めにお召し上がりください。
- 本品は天産品ですので、色・味・においなどが多少異なることがありますが、品質には問題ありません。
- 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤が封入されておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。
©2001 - 中屋彦十郎薬舗株式会社 All rights Reserved.
プライバシー保護方針 特定商取引法に基づく表記 
本社・薬局/通信販売
〒920−0981 石川県金沢市片町1丁目1-29 TEL 076-231-1301/FAX 076-231-1306
工場
〒921−8117 石川県金沢市緑が丘21-9 TEL 076-245-3366
|